|
|

元禄江戸俳壇の研究
蕉風と元禄諸派の俳諧 |
| |
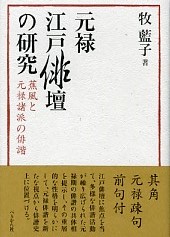 |
元禄江戸俳壇の研究
A5判・292頁
ISBN4-8315-
ISBN978-4-8315-1394-6
C3091
2015 年発行
|
元禄俳諧の諸派とは別個に論じられることの多かった蕉風俳諧を、元禄俳諧から享保俳諧に至る俳諧史の連続性のうちに相対的にとらえ、元禄俳諧を新たな視点から位置付ける。
●目次●
はじめに
凡例
第一章 蕉風における其角の俳風とその変遷
第一節 其角の「情先」
一 蕉門における景情論
二 支考の「姿先情後」
三 其角の景の詠み方
四 其角の「情先」と本情論
五 其角の「情先」の意義
第二節 其角の不易流行観
一 『末若葉』跋文の其角加筆の問題
二 其角の不易流行観の特徴
三 其角の「不易」の根拠
四 其角の新しみの追求
五 沾徳の俳論との類似性
第三節 謎の発句
一 貞門俳諧における「ぬけ」の問題
二 和歌・漢詩の手法と「ぬけ」
三 発句の「ぬけ」の本質
四 「ぬけ」の謎句
第四節 其角と「洒落風」
一 『鳥山彦』の俳諧史観
二 後世におけるいわゆる「洒落風」
三 其角の「しゃれ」
四 沾徳の「しゃれ風」
第二章 初期俳諧から元禄俳諧への展開
第一節 詞付からの脱却―「ぬけ」の手法を中心に
一 貞門の「ぬけがら」
二 談林の「ぬけ」
三 詞付の「ぬけ」
四 「ぬけ」の展開
第二節 元禄俳壇における「うつり」
一 元禄疎句と「うつり」
二 元禄当流と蕉風における「うつり」の差異
三 景気の句と「うつり」の関係
四 前句付派の「うつり」
第三節 元禄俳諧における付合の性格―当流俳諧師松春を例として
一 松春の俳諧活動
二 『俳諧小傘』の付合手法
三 『俳諧小傘』の「付心詞」
四 「八衆見学」歌仙に見る元禄風
五 『白うるり』の高点句の特徴
第四節 「元禄当流」という意識
一 俳諧における三都の意識
二 三都の俳壇状況と「当流」
三 「当流」の意味するもの
第三章 元禄期江戸の前句付
第一節 調和における前句付の位置
一 俳諧撰集と前句付高点句集における作者層の違い
二 前句付の興行形式
三 調和の俳諧活動における前句付興行の意義
第二節 不角の前句付興行の変遷とその意義
一 前句付高点集の形式と変遷
二 一晶・調和の前句付との関係
三 元禄宝永期の前句付の動向
第三節 享保期の不角の月次興行の性格
一 不角歳旦帖の特徴
二 月次興行の性格の変化
三 月次発句高点集の作風
四 『ことぶき車』の作風
第四節 不角の俳諧活動を支えた作者層
一 門人の開拓(一)―信州野沢の場合
二 門人の開拓(二)―丹後宮津の場合
三 常連作者層の動向
四 不角前句付興行・月次発句興行の意義
おわりに
索引(人名・書名/初句)
|
|